各施設の特徴
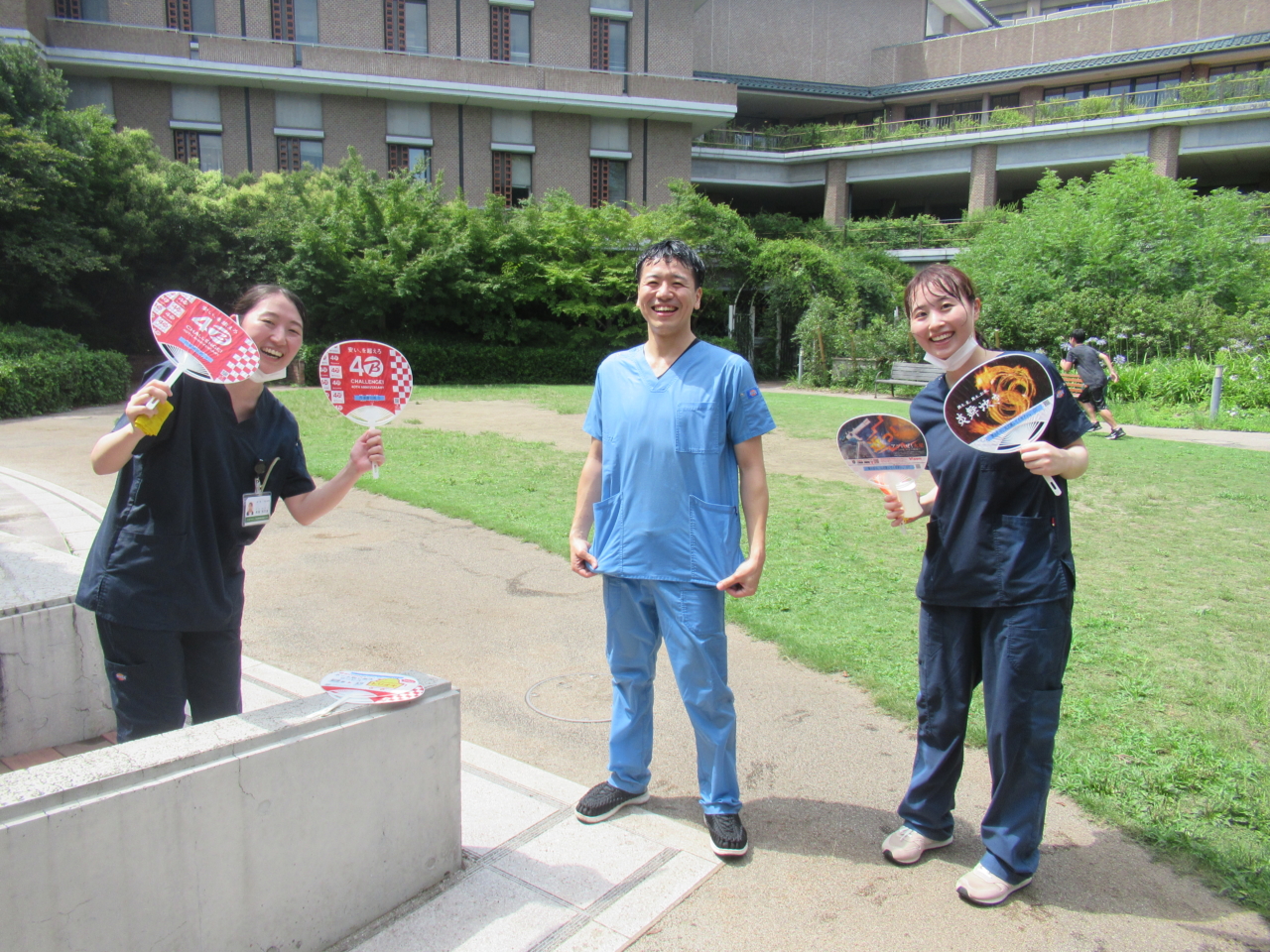
(1)地方独立行政法人岡山県精神科医療センター 児童精神科・精神科・心療内科
岡山県精神科医療センターは、県内唯一の児童精神科入院病棟(院内学級併設)があり、「岡山県子どもの心の診療ネットワーク事業」の拠点施設です。また常時対応型精神科救急基幹施設でもあり、24時間365日、子どもを含むすべての年代の精神的危機に対応をしています。小学校教員1名、中学校教員2名が勤務する院内学級があり、看護師、精神保健福祉士、心理士、作業療法士と多職種が配属されチーム医療をおこなっています。児童相談所、児童自立支援施設、家庭裁判所、保健所、支援学校等に非常勤医を派遣しており、多様な子どもを、地域全体で支える仕組みづくりを行っています。
児童精神科領域以外では、精神科救急、依存症医療、総合病院連携、在宅医療など多様な精神科医療をおこなっており、成人医療との連携により、家族の支援をより効果的におこなう土壌があります。
医療、保健、教育、福祉、司法など多岐にわたる機関と連携するネットワークの中で研修を積むことにより、子どもを中心に、幅広い視点をもった専門医を育成します。
(2)まな星クリニック 児童精神科・精神科
まな星クリニックは、児童発達支援センター、相談支援事業所、就労移行事業所などを併設した発達障害(自閉スペクトラム症等)に対する早期診断・早期療育からはじまり、青年期の自立にいたるまでのライフステージ支援とメンタルヘルス問題への治療介入を行っている多機能型児童精神科診療所です。 初診の8割が就学前の幼児であり、就学まで言語療法士、作業療法士による個別療育や心理士による小集団ソーシャルスキルトレーニングなどの療育支援を、学童期・思春期には、必要に応じてCBTベースの目的別心理教育プログラムを実施しています。また親支援にも力を入れており、発達障害対応の心理教育だけでなく、親子相互交流療法(PCIT) 、子どもと大人の絆を深めるプログラム(CARE)にも取り組んでいます。
現在、常勤児童精神科医師4名、非常勤児童精神科医師6名、コメディカルスタッフ30名以上が多職種で協働し、保健所や児相、学校などの他機関と連携し地域支援の一端を担っています。
(3)岡山大学病院 精神神経科
高次医療機関の精神科として、閉鎖病棟14床を含む28床を有し、難治な精神疾患の診療とともに、身体疾患を併存した精神障害の方の診療にも力を注いでいます。このため、重度なやせをきたした摂食障害の入院を数多く受け入れています。統合失調症、気分障害を始め、対応する疾患は多岐にわたり、外来では多くの性別違和の受診があることも特徴です。慢性疼痛や睡眠障害に対する認知行動療法プログラムなども実施しており、エビデンスに基づいた診療を経験することができます。また脳神経画像や長時間ビデオ脳波など脳器質性異常の鑑別に習熟した医師が活動しています。医師と公認心理師が協働するリエゾンチームが活動しており、他科と連携して患者と家族を支える診療にも力を入れています。子どものこころの問題に対処する時、アットリスク・メンタルステイト(ARMS)の理解や精神疾患との鑑別、保護者アセスメントと理解は必須であり、精神科領域への理解は実臨床を行う上で重要です。
(4)こども総合相談所(児童相談所)
こども総合相談所は、政令指定都市である岡山市に設置された児童相談所です。児童精神科医師が勤務しており、児童虐待への対応、発達障害の相談や知的障害児の療育手帳の判定など多岐にわたる業務を行っています。
児童福祉法上の一時保護所があり、要保護児童を保護しており、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設等と連携して支援を行っています。児童の非行問題にも関与しており、家庭裁判所等との連携をおこなっています。
要保護児童は心的トラウマ問題を有することが多く、トラウマインフォームドケア(TIC)、トラウマフォーカスト認知行動療法(TF-CBT)を実施しており、親子相互交流療法(PCIT)などの親支援を「子どもの心の診療ネットワーク」の医療機関と連携して実施しています。
(5)岡山大学病院小児心身医療科/小児科
小児の心身症の診療に力を入れており、起立性調節障害、慢性頭痛、過敏性腸症候群などの機能性疾患や摂食障害の方の診療を経験できます。また、教育機関とも連携しており、不登校の相談も行っています。公認心理師と小児科医が協働して診療にあたっており、お子さんへの各種心理療法を行うとともに、ご家族と家族面接を並行して環境調整にも力を入れています。
- 不登校に至った起立性調節障害の方
- 食事を食べることへの恐怖を訴える摂食障害の方
- 不登校の背景に発達の課題がある方などのお子さんの診療を見通しを持ってできるように研修していきます。
また、当院の特徴として、重症な先天性疾患や悪性疾患のお子さんの全人的な診療にも参加しており、治療中の不安への対応や治療後の学校復帰への支援なども経験できます。
(6)旭川荘療育・医療センター
当科は小児科、整形外科、小児神経科、歯科の常勤医師が在籍する障害福祉分野を対象とした総合病院で、当科は発達障害の外来診療を専門としています。初診時は主診断が発達障害となる未就学児が診療の主体となりますが、長く経過を追う中で学童期、思春期、青年期、成人期の課題や保護者の悩みにも寄り添い治療的介入を行っています。療育としては就学まで心理士、言語聴覚士、作業療法士による個別療育、心理士による集団療育を行っています。子どもの心の診療ネットワークの医療機関と連携して親子相互交流療法(PCIT)や子どもと大人の絆を深めるプログラム(CARE)を実施しています。主に取り扱う疾患は自閉スペクトラム症ですが、経過の中で注意欠如多動性障害、学習障害など学習面での課題、虐待や不登校などの問題も多く見られます。
児童発達支援センター(2施設)、児童発達支援事業所(2施設)、乳児院、保育園など多岐にわたる関連施設があり、見学研修も可能です。
;\


